- 「住宅を購入する際、贈与税が非課税になるって聞いたけど、よくわからない…」
- 「利用する際に注意することってあるの?」
この記事はこんな疑問や悩みを抱えている方に向けて書いています。
こんにちは、ケンちんです。
現在、住友林業で建てた家を建築中。
妻と子供2人の計4人で暮らしている30代男性です。
家を購入する際に、ローンの支払いが続けられるか不安という方は少なくないと思います。
そんな時に、利用できる制度として住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置があります。
この住宅贈与非課税制度を簡単に言えば、「住宅の頭金に使用するなら、1000万円まで贈与税を非課税にするよ!」っていう制度です。
ただ、この住宅資金贈与非課税制度は対象になる人・住宅の条件など複雑で理解するのにとても時間がかかるんです。
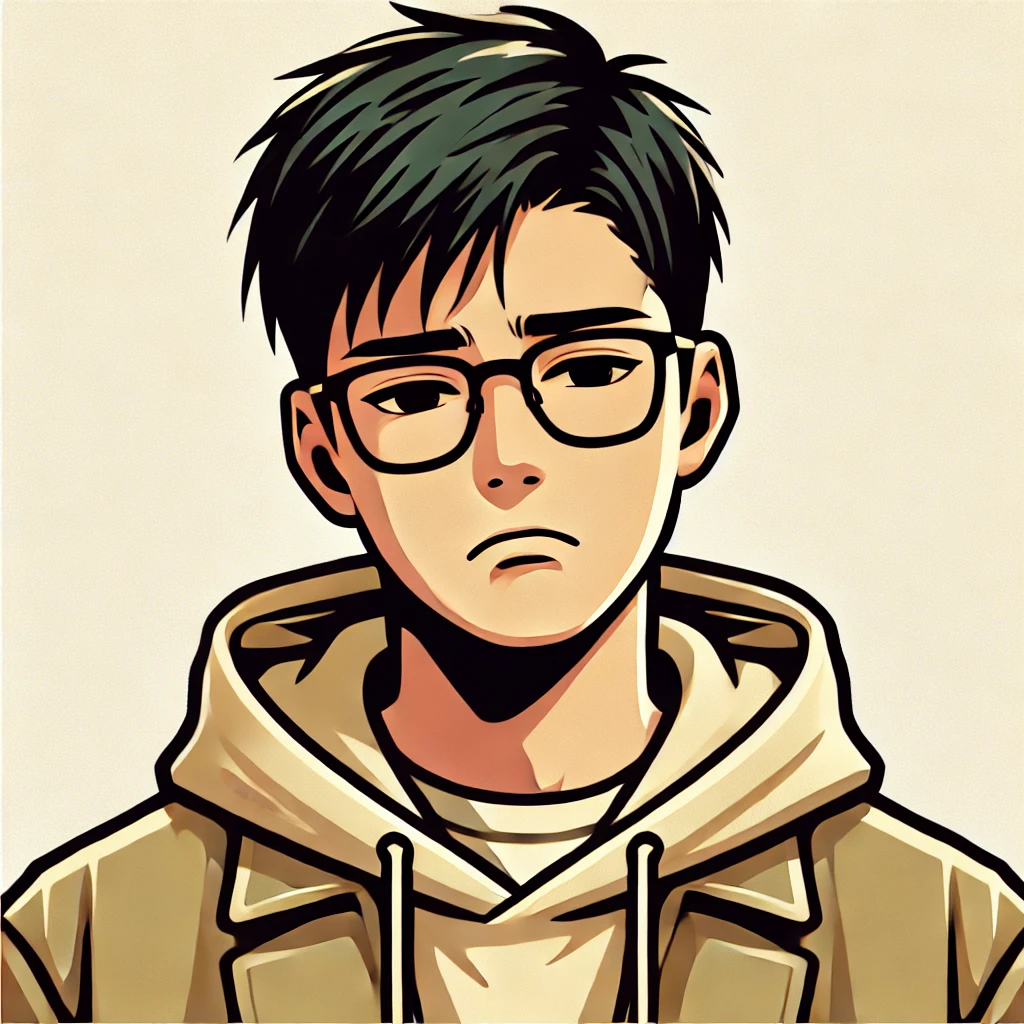 ケンちん
ケンちんいろいろなHPをちょっとずつ調べたりして、とても面倒くさかった…
そこで、本記事では「住宅資金贈与非課税制度の概要」「対象になる人・住宅の条件」「注意点と申告方法」の3つに絞ってわかりやすく解説していきます。
もし今家の購入に迷っているなら、制度を使えるかどうかで数百万円単位で違いが出てきます。
知らないと損をする制度なので、ぜひ最後まで読んで、住宅資金を大幅に減らしてくださいね。
住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置とは?


制度の概要
住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置は、父母や祖父母などからもらったお金を、家を買う資金(または土地を買う資金)にあてるときに、一定額まで贈与税がかからなくなる制度です。
この制度、最大で1,000万円までは贈与税が非課税になります。
ただし、この非課税 上限は法律の改正によって変わることもあるので、利用する際は、最新情報をチェックしてください!
制度が適用される条件
制度が適用される条件を解説します。(2025年2月9日時点)
条件には受贈者の条件、住宅の条件(新築または購入)、非課税となる金額の上限があります。順に解説します。
※詳しい要件についてはかならず「国税庁のHP」を確認するようにしてください。
贈与者 ・・・ 贈与税を渡す人(父母、祖父母)
受贈者 ・・・ 贈与税を受け取る人(子、孫)
受贈者の条件
以下の条件に該当する受贈者は本制度を利用できます。
- 贈与者の直系尊属()にあたる
- 贈与された年の1月1日時点で18歳以上
- 合計所得金額が2,000万円以下
- 2009年以降に本制度を利用したことがない
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること
父母・祖父母など自分より前の世代で、直通する系統の親族(配偶者の父母、祖父母は対象外)
住宅の条件(新築または購入)
以下の条件に該当する住宅は本制度を利用できます。
- 日本国内にある
- 登記簿上の床面積が40mm²~240mm²かつ、その1/2以上の面積が受贈者の居住スペースである
注)中古物件や増改築の場合は様々な条件があるので、都度確認が必要。
非課税となる金額の上限
省エネや耐震性、バリアフリー性の高い住宅(以下の条件に該当する場合)は1000万円まで贈与税が非課税となります。
それ以外の場合でも上限が500万円までは贈与税が非課税となります。
- 断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上
※中古物件、増改築の場合は条件が緩和される。() - “耐震等級:2以上” または “免震建築物(建物の下に免震装置が設置されている)”
- 高齢者等配慮対策等級<専用部分>3以上
「断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上」と緩和される。
制度を使わずに贈与した場合にかかる税額シミュレーション
ちなみに、両親(直系)から贈与をされた場合、本制度を利用しないと以下の贈与税が発生します。
1000万円の場合 ・・・ 177万円の課税が発生
500万円の場合 ・・・ 58万5千円の課税が発生
1000万円(贈与税)110万円(基礎控除)=890万円(課税対象の金額)
{890万円0.3[30%]()}()
()の値は国税庁の特例贈与財産用速算表より引用(URL:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm)
つまり、本制度を利用しないと最大で177万円を損することに!
本制度によってこれだけの課税を抑えることができるので、知っているだけでかなり得することがわかりますよね!
利用するうえでの注意点


制度には期限がある(2025年2月時点)
本制度の適用期限は2026年12月31日までとなります。
本制度の利用を考えている人は、上記の期限を考慮したうえで家の購入を検討してください。
※最新の情報は「国税庁のHP」でご確認ください。
贈与を受けたお金はかならず住宅(または土地)の頭金に使うこと
当然ですが、贈与を受けたお金は住宅(または土地)の頭金に使うことが条件となります。
受け取った贈与を「外構」()や「家具、家電」などに使用しても本制度は適用されないので注意してください。
土地に適用は可能だが、住み始める時期に注意しないと適用対象外になる可能性がある
本制度は「住宅と共に土地を購入した場合」や「住宅の建築前に先行して土地を購入した場合」どちらも適用されます。
ただ、注意点としては
- 土地のみの購入では適用されない
- 土地の贈与には適用されない
- 土地購入時の翌年3月15日までに取得した土地の上に住宅用家屋を新築(新築に準ずる状態として、屋根またはその骨組みが完成している)できている必要がある
特に最後の点については注意が必要です。
土地は購入したが建物の設計がなかなか進まず、期限を過ぎてしまい本制度を利用できなくならないようにしてください。
住宅ローン減税の金額が少なくなる
本制度を利用すると、住宅ローン減税制度()は
となり、ローン減税で控除される金額が少なくなってしまいます。
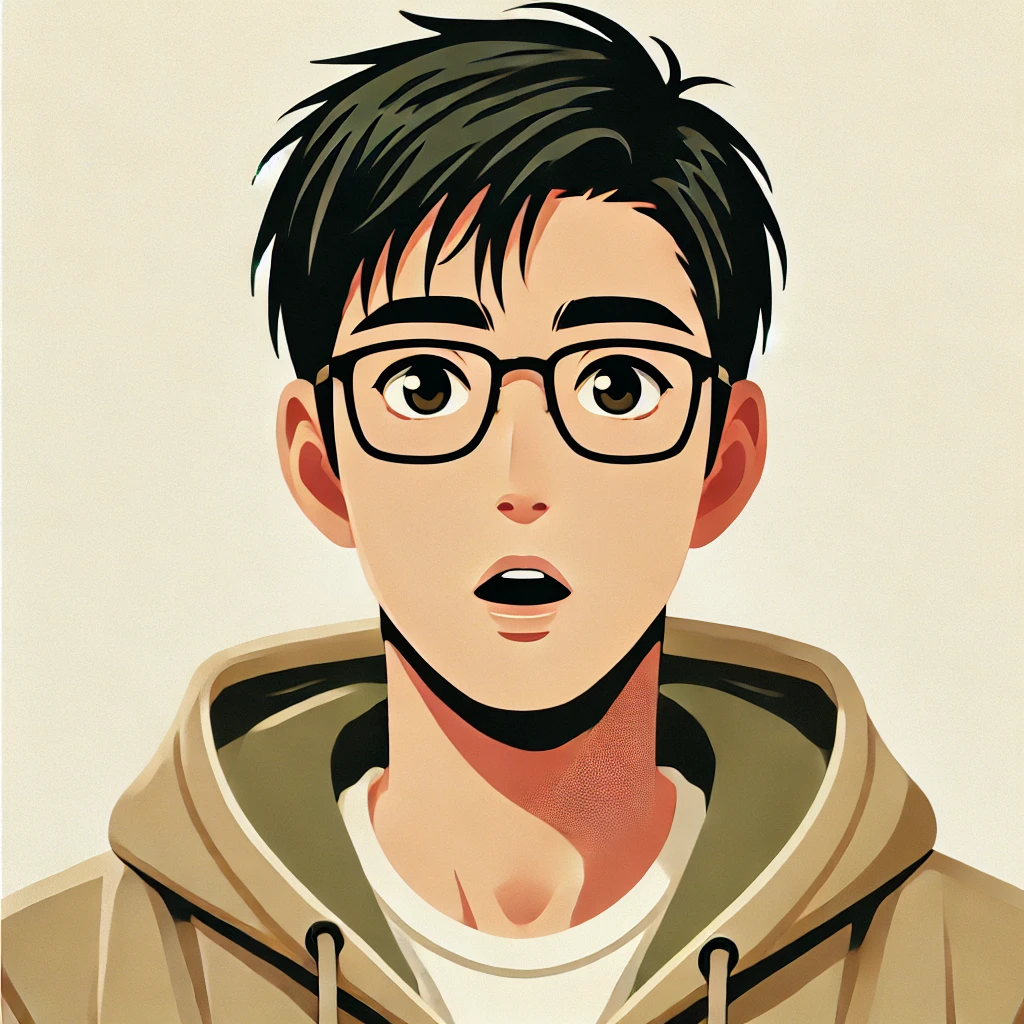
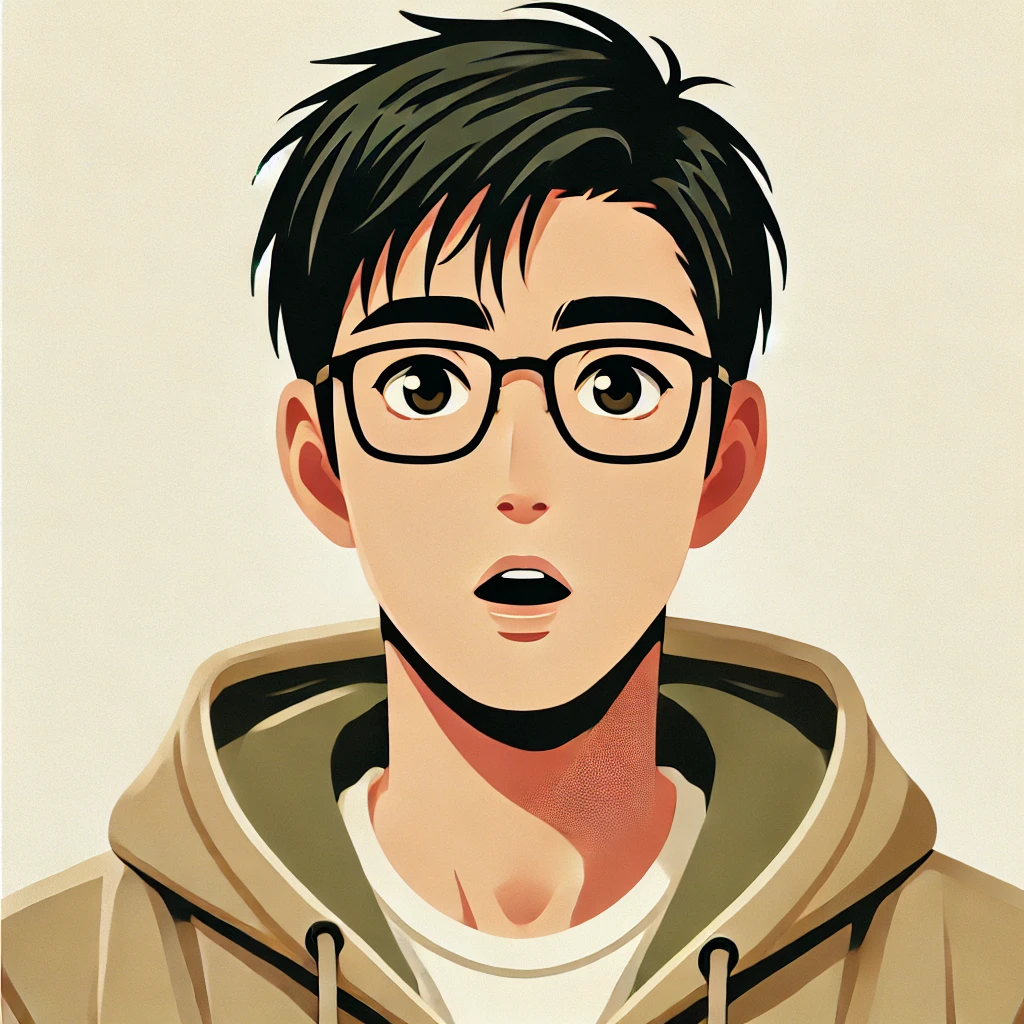
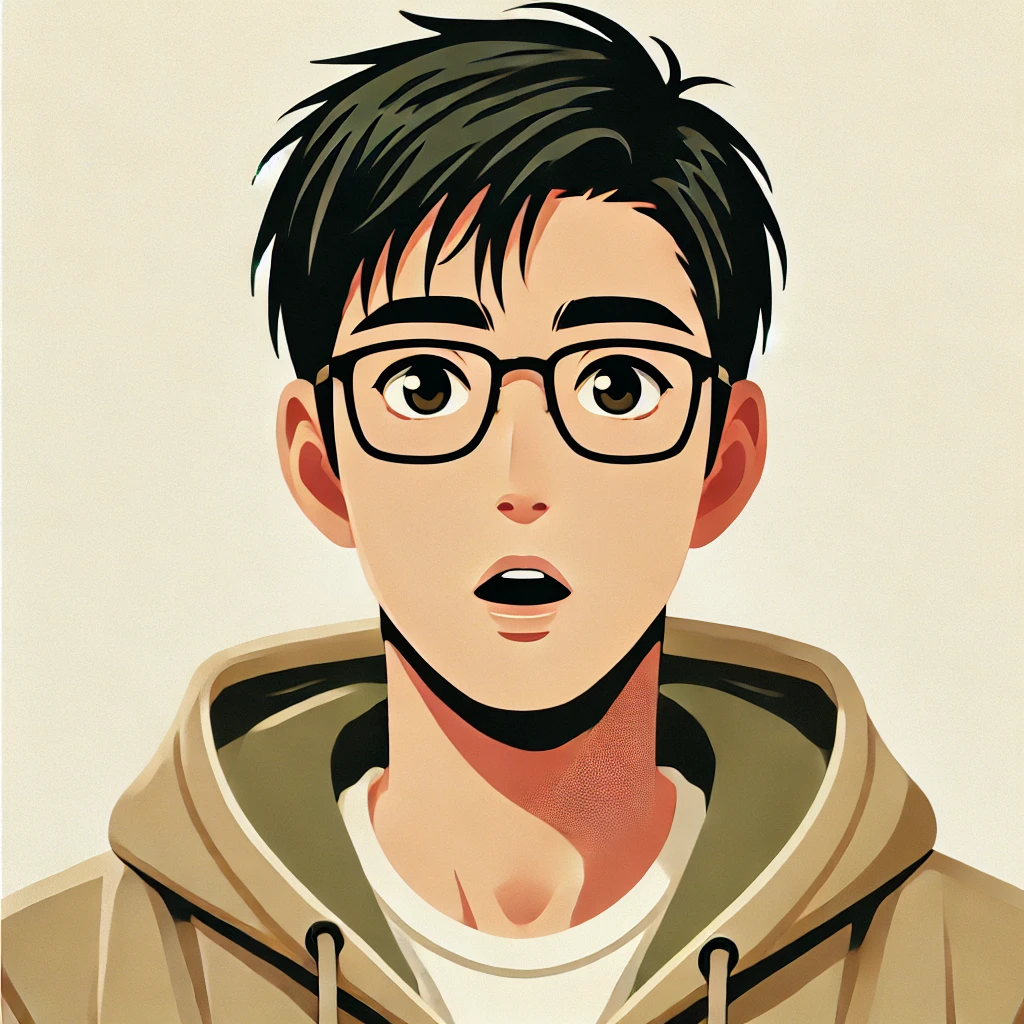
それでも贈与税の非課税制度を受けたほうが、はるかにお得です!
住宅ローンの一部が次の年の所得税や住宅税から控除される制度(最大0.7%)
控除率や控除期間などは条件により異なるが、最大で455万円()の減税が可能になる。
:「長期優良住宅」「低炭素住宅」「19歳未満の子を有する人、または夫婦のいずれかが40歳未満の人」全てに当てはまる場合
小規模宅地等特例制度との併用は不可
本制度は小規模宅地等特例制度()との併用はできません。
亡くなった人が自宅として使っていた土地を、配偶者もしくは亡くなった方と同居していた親族が相続した場合、土地の評価額が8割引きになる特例。
土地の評価額が最大80%減となるため、相続税を大幅に減らすことが可能。
小規模宅地特例制度の要件の中に「被相続人が持ち家を持っていないこと」という条件があり、住宅を購入してしまうと
その条件から外れてしまうためです。
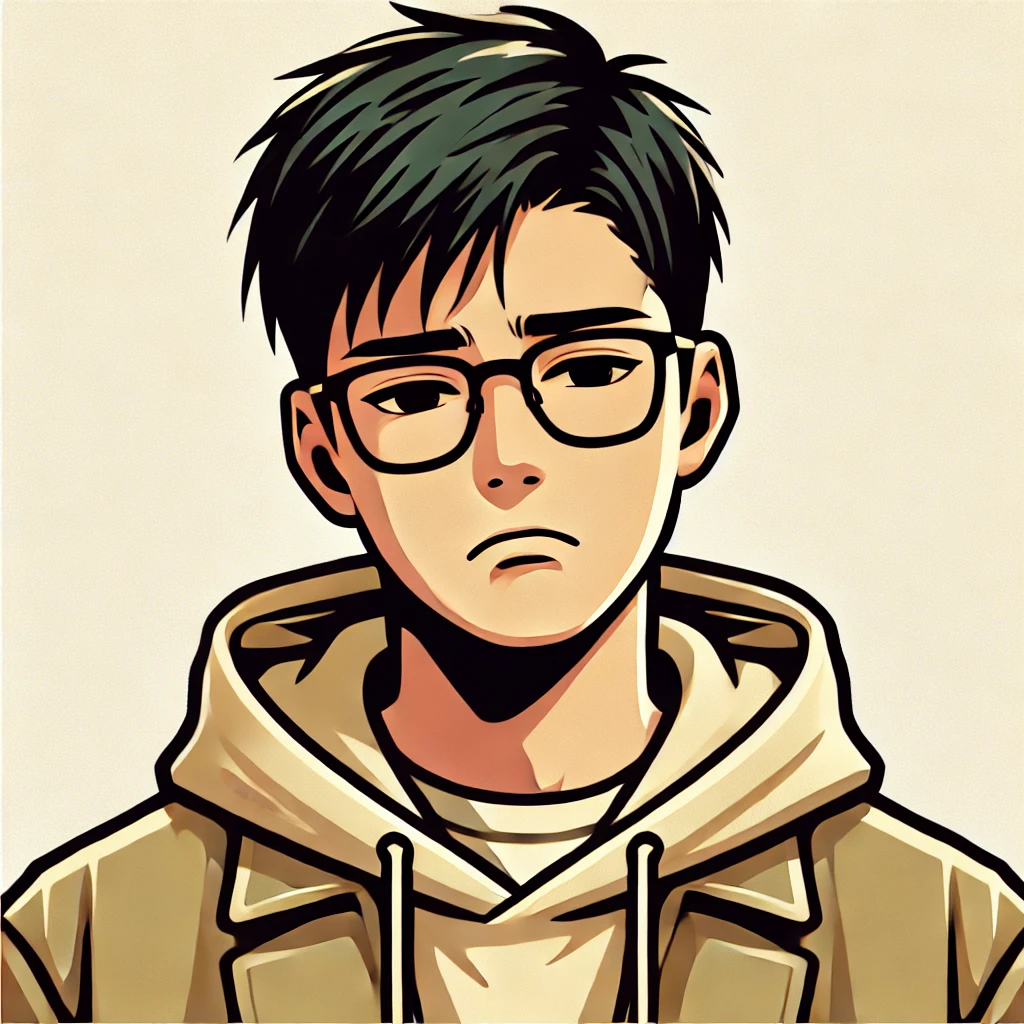
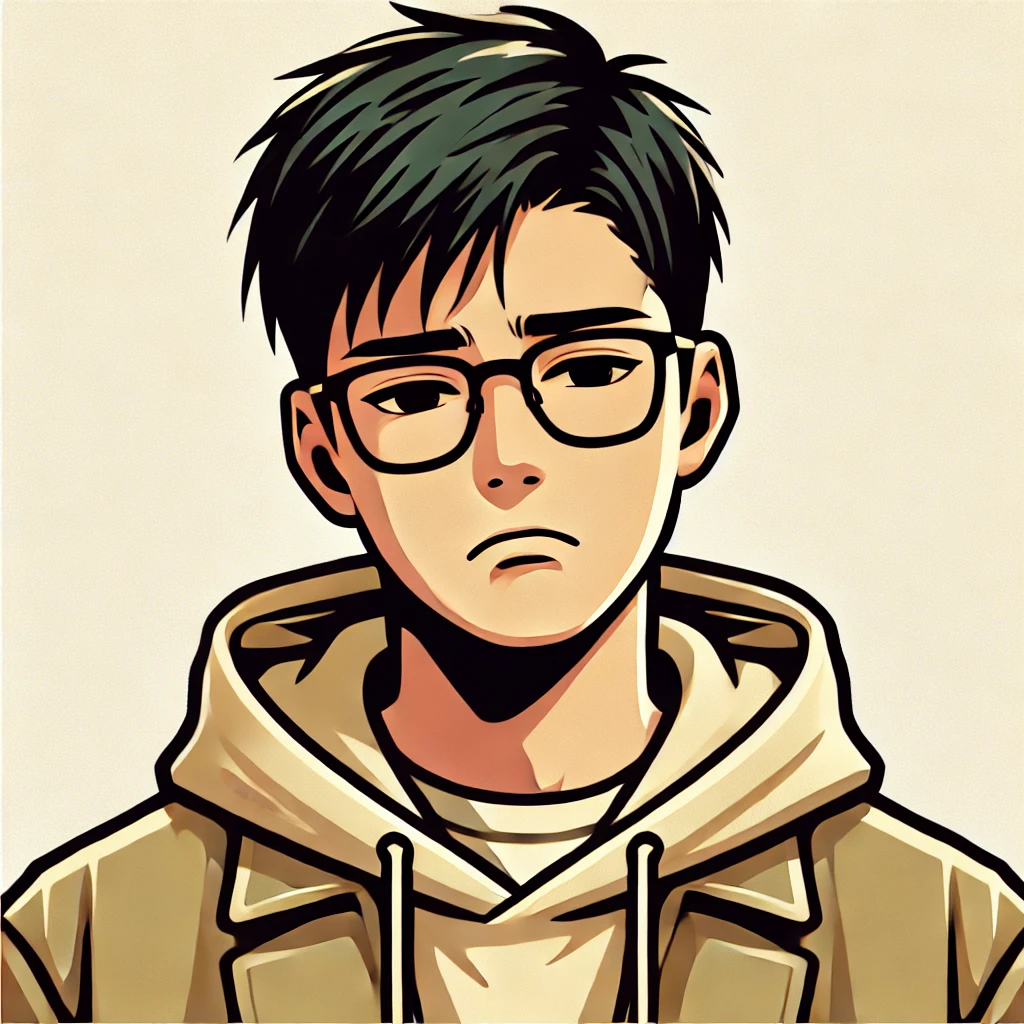
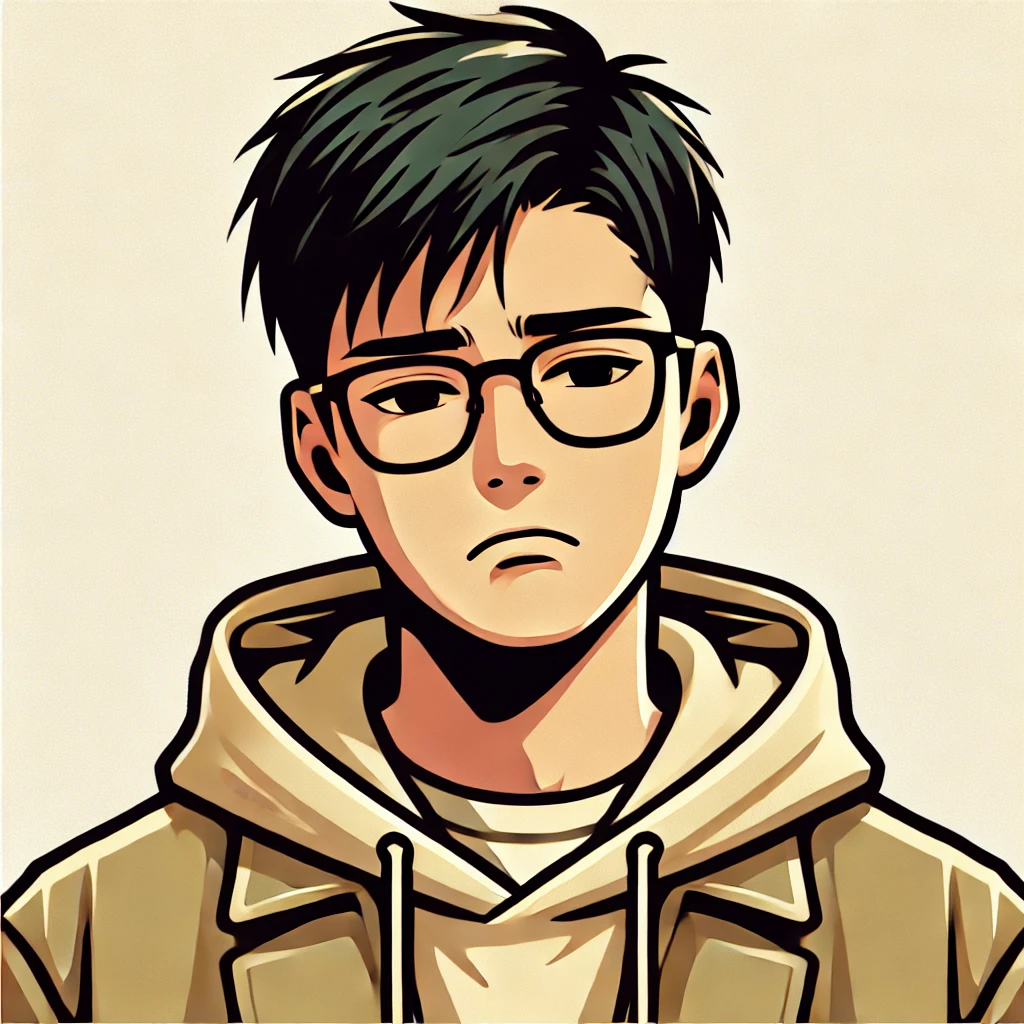
「住宅資金贈与税非課税制度を利用したことで」というより、「住宅を購入してしまう」と小規模宅地特例制度が受けられなくなるということ。
暦年贈与【基礎控除】との併用は可能
暦年贈与【基礎控除】()との併用が可能ですので、最大で贈与税が1100万円までは課税されません。
住宅資金贈与の非課税制度は税務署への申告が必要ですが、暦年贈与は税務署への申告が不要です。
贈与税にも基礎控除があり、年間で110万円までの贈与に関しては非課税となる。
暦年贈与はその基礎控除を利用して、年間110万円以内で複数年に渡り、贈与を繰り返すこと。
贈与税の申告方法の流れ
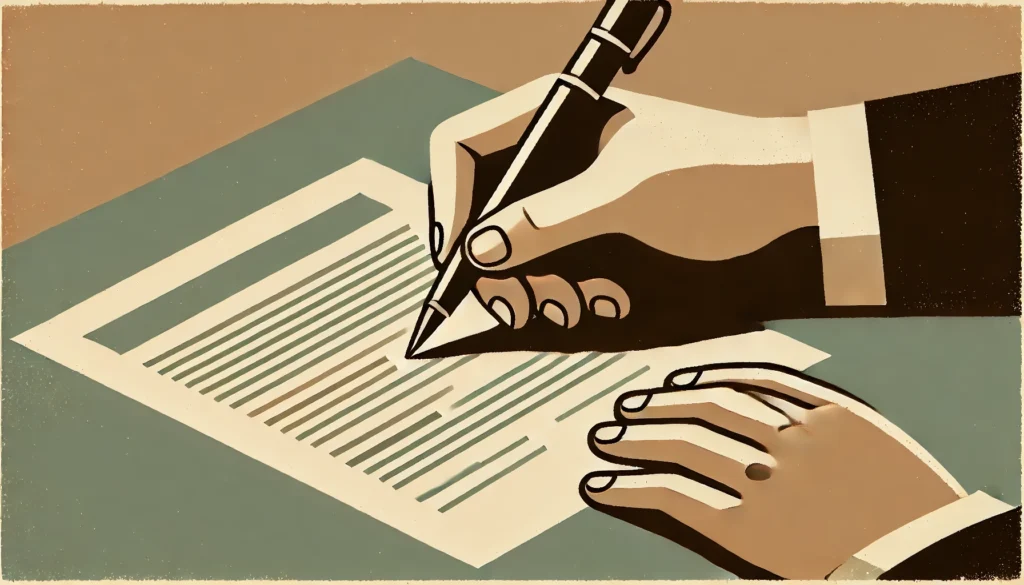
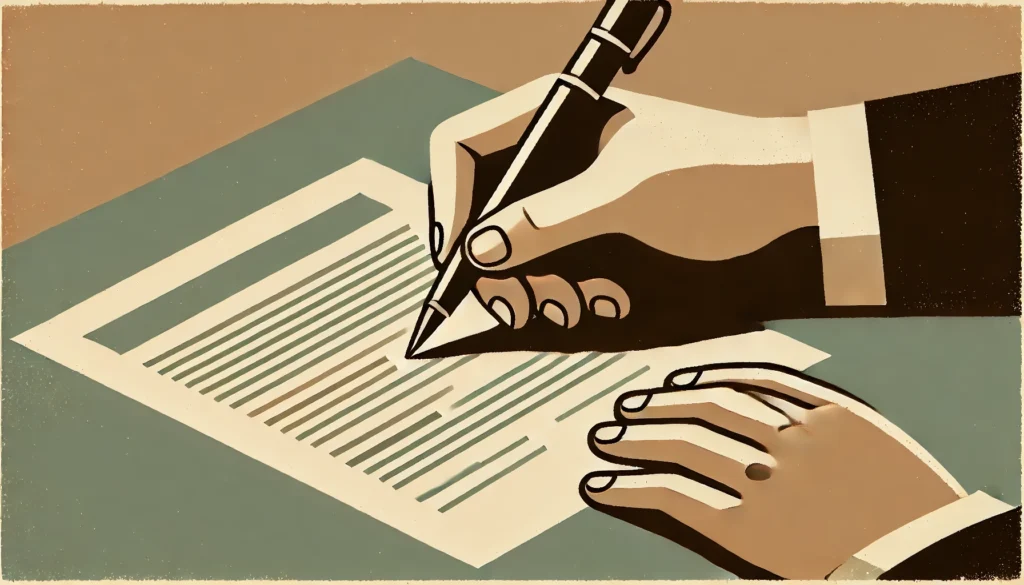
本制度を利用する場合は贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までにかならず税務署へ申告が必要になります。
申告を行わないと、贈与税が発生しますので注意してください。
必要書類は以下のとおりです。
- 贈与税の申告書
- 戸籍の謄本
- 源泉徴収票 (所得税の確定申告した場合は不要)
- 住宅用家屋の新築、取得に関する必要書類()
- 高性能住宅(省エネ、耐震、バリアフリー)であることがわかる証明書()
・請負契約書
・登記事項証明書 ・・・など
・住宅性能証明書
・建設住宅性能評価書の写し
・住宅省エネルギー性能証明書
・「長期優良住宅建築等計画等の(変更)認定通知書の写し」と「住宅用家屋証明書(写し)または認定長期優良住宅
建築証明書」 ・・・など
【まとめ】適用条件と注意事項をチェックして、利用できる場合は必ず利用しよう!
住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置はお得に家を建てたい人にとっては、とても魅力的な制度です。
必要書類の準備や税務署への申告は少し手間かもしれませんが、最大で177万円の節税になり、住宅ローンの頭金を大幅に抑えることが可能となります。
ただし、本制度を利用する際には、適用条件が複雑で注意事項も多いため本記事を活用するなどして、事前に詳細を確認いましょう。
また、本制度の上限金額や、適用期間などは毎年変わることもあるため、「国税庁のHP」にて最新の情報をしっかりと確認してください。
もし家の購入を考えているなら、ぜひこの制度を一度チェックしてみてくださいね。

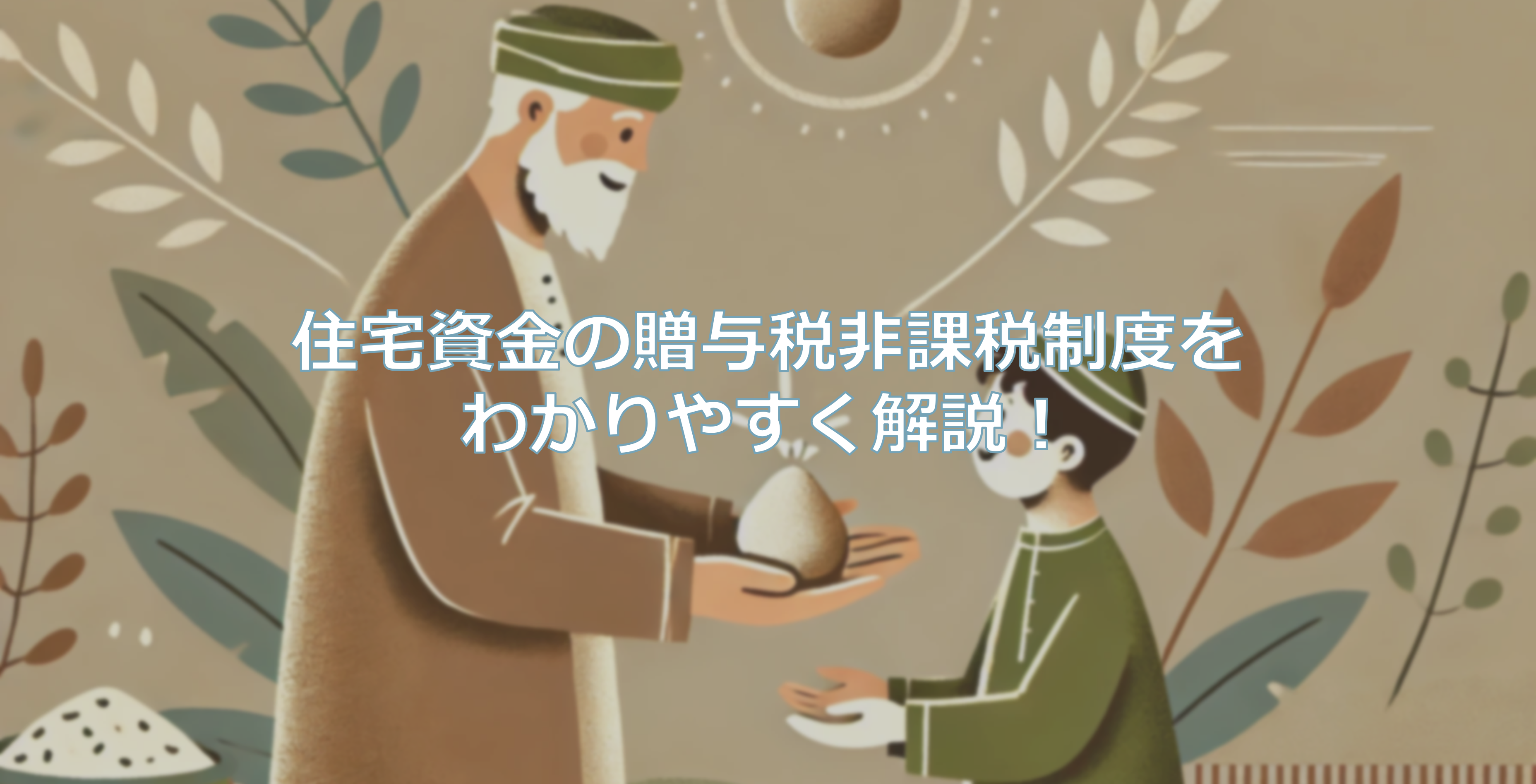
コメント